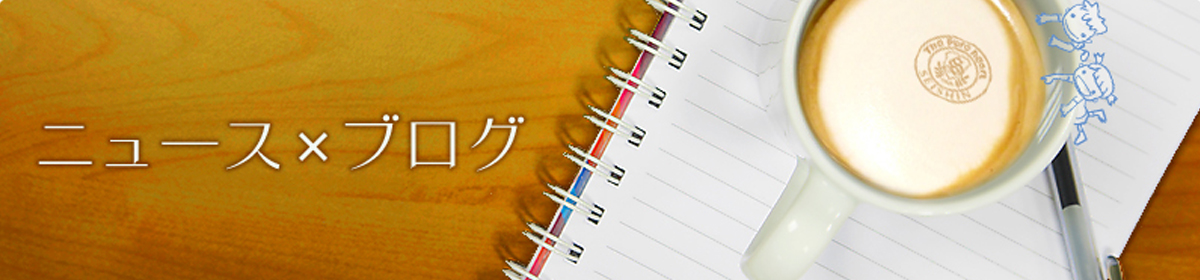年長では、<壁画制作プロジェクト> がすすんでいます。
先日、そのための色づくりをする「いろのじっけんしつ」が、
保育室の中にできました。
今後、「前橋の町の色さがし」に出かける予定です。
さて、ここから、どんな色が生まれるでしょうか?
カテゴリー: こども(プロジェクト)
「ライブペインティング」@弁天通り(「広瀬川アート散歩」)
7月14日(土)に行われた、「広瀬川アート散歩」のライブペインティングに
年長さんが参加して、パフォーマンスしてきました。
会場は前橋市内中心部、「弁天通り商店街」です。
地元の方ならご存知の方も多いでしょう。
最近は、CMや映画など数多くの撮影場所にもなっている
情緒あふれる商店街です。
そこに、先日下地を塗ったキャンバス生地を広げて準備しました。
(お寺さんの入り口でスミマセン。ありがとうございました)

早速、オレンジやピンクのカッティングシートを追加して貼っていきます。

それから、下地を「川」や「道」に見立てて、歩きました。
そのまま歩くのではなく、子どもたちの足跡を絵の具で残します。


黄色と緑色が出会ったり、青色と黄色が出会ったり。偶然のような
必然のような 出会いから あっという間に世界が変わっていきました。

そして、ここからがさらに おもしろかったところです(きっと!)。
貼ってあった、カッティングシートを見つけて、それを剥がしていくのです。
オーッ!! なんだなんだ!? 何かがあらわれてきたよ!


そこには、いろいろなカタチや色が隠れていました!
これは、子どもたちが、実際に広瀬川を散策して、見て、感じて、
イメージしたものを形にして、最初に張っていたものです。
私たちが広瀬川沿いや商店街を歩くと、再発見する楽しさがあるように、
キャンバスに描いた「川」や「道」の中で、子どもたちも
新たなおもしろさを見つけていく、そんなパフォーマンスでした。
弁天通商店街に掛けていただきました。
よかったらお出かけください☆
+++++++++++++++++++++++++++++++++
お越しくださったみなさま、おうちの方、ありがとうございます。
地元の商店街のみなさま、どうもありがとうございます。
実行委員のみなさま、どうもありがとうございます。
清心幼稚園スタッフ一同
【年長】「まちたんけん」×「広瀬川ライブペインティング」
「広瀬川アート散歩」が7月14日(日)と15日(月・祝)に前橋市内で行われます。
14日には多くの方が広瀬川周辺でスケッチをされるそうです。
また、14日の12:00~13:00の間、弁天通り周辺で行われる
ライブペインティングに清心幼稚園の5歳児(年長)が参加します。
これまでに、子どもたちと実際に広瀬川を探検して、見つけたものや
イメージしたものを、子どものなりの表現で制作する予定です。
当日は時間が限られるため、現在子どもたちと園で少し制作を始めています。
10mのキャンバスが今回の素材。とても大きな画面なので、
私たち保育者も試行錯誤しながらの協同作業です。
今日は、一部にベースの色を塗って、鑑賞し合いました。
さて、これからどんなふうに展開するでしょう。とても楽しみです!
7月14日のライブペインティング会場では、画材メーカーさんの
ワークショップも多数出展されるそうです。みなさんもぜひ遊びに
お出かけになられてはどうでしょう??
【年長】まちたんけん③「広瀬川へ」
今日は、広瀬川の探検に行くことになりました。
前回の「地図ないの??」の声を生かして、今回は「地図をもっていこう!」という作戦。
ボール紙に町の地図を貼って、それぞれが持って歩きます。
自分に必要な準備を自分でやっていくのも5歳児ならではですね。
こちらは保育室に貼ってある地図です。
住宅地図をつなげています。青くみえるところが広瀬川。
それと、赤い四角で囲っているところが見えますかー?
左下の方角(南西)です。そこが出発地の清心幼稚園☆
距離感や方向が一目瞭然。道もきっとよく分かるね!
このように、行ってみて、歩いてみて、地図を見て、
それから また いろいろやってみて、体感的に、体験的に、
「知っていく」「分かっていく」ことが大切だと考えています。
【年長】「まちたんけん②」けんちょうへいく。
先週に引き続き、「まちたんけん」へ。
「けやきウォーク」まではたどり着けなかったので、
今日はどうしても目的地まで行きたい!
子どもたちからそんな思いがいっぱい伝わってくる中、
県庁まで探検です。32階の展望フロアーまで行くと・・・
「ようちえんがみえるー!」
「アレ、しょくじゅ(植樹)のこうえんじゃない?」 「ほんとだー」
「あッ、でんしゃだー!」 「えーッ??」
「どこどこ?」「あそこーッ」 「みえたー!!」
「りょうもうせんだ!」 「まえばしえきだ!」
この日の天気はあいにくの薄曇り。視界もさえません。
でも、子どもたちの眼には関係がなかったようです。
さて、どのくらい こうしていたでしょうか。
「時を経つのも忘れて」とは、こういうことなんだろな。
【年長】「まちたんけん」へ
子どもに「町」って知ってるか聞いたところ、「けやきウォーク」という声が一番多かった。
どこにあるのかも分かっているらしい。 そこで、行き先は「けやきウォーク」に!
明日はバラ園。その次は県庁に行きたいのだそう。 いろいろ知ってるなァ・・・
さあ、しゅっぱつ!!
子どもの記憶する道を 聞きながら、歩いていくと・・・
んー、ここはどこー??
おッ! 川にたどり着いたみたい。
しばし、休憩。
すると、ちょうど 幼稚園へもどる時間になりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
幼児A 「まだ、ついてないよー!」 (たしかに)
幼児B 「地図ないの??」 (そう、もってないんだ。でも、その気づきがいいよね!)
納得いかない様子が あちこちに見えます。
どうやら、思っていた方向と 逆に向かって歩いてきたようです。
保育者 「今度は地図を持ってこよ!」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちょっと 遠回りをしているのかもしれません。
保育者が最初から道案内をしたり、地図を用意すれば、
こうした展開にもならないでしょう。
でも、子ども自身のこうした気づきが、
納得ある次の活動へとつながっていくのだと思います。
イワシのカラダはどこへ?(節分番外編)
イワシのアタマは、節分用の「ヒイラギイワシ」になりました。
では、カラダはというと・・・
木切れを燃やして、
木炭に火を点け、
七輪で焼いて、
ひとつまみずつ 分け合って いただきました!
気持ちのいい豆まき。
園庭に とつぜん現れた!
年中さんや年少さんが準備していた「ひいらぎイワシ」や福豆の買出しを
遠目に見たり聞いたりしていた 年長さんの何人かが変身。
「おにはー そとー!」 「ふくはー うちー!」
オニも負けていません。 豆を拾って、すぐさま投げ返します。
あっ、2階のベランダからも豆が飛んできた!
【年中】豆まきの準備をする②(ひいらぎイワシを作る)
園庭でイワシをさばくことになった。
なぜなら、イワシのアタマが必要なのだ。
イワシをよくみてみる。 そして切ってみる。
そのアタマに、普段遊びで使っている木切れを 刺してみる。
ヒイラギの葉が見当たらず、 代用品を見つけてきたのだ。
できあがったものをこんな風に並べていた。
これから、どうなるのかなァ、と思ってみていると、
保育室の前に砂山を作って、各部屋ごとに立てていた。
こうすれば、きっと鬼も部屋の中には入ってこないだろう。
なかなかの思いつきだと思った。
【年少&年中】豆まきの準備をする①(豆とイワシの調達)
年中の子どもたちから、鬼を追い払うには 「豆とイワシが必要」との話がでた。
「じゃあ、買いに行こう!」と、年中さんと年少さんが協力して出かけることに。
そこで、豆チームは、「フレッセイで売ってる」と、フレッセイ(スーパー)へ。
一方、イワシチームは、魚屋(「魚健」さん)へ。
途中、道が分からなくなって迷っていると、秋葉写真館の秋葉さんが
地図を見ながら教えてくれた。
「魚健」さんに着くと、イワシを買いに来たはずだけど、
子どもたちは いろいろな魚たちに興味津々。
子どもたち:「これなに~?」(アサリを見つけて)
すると、おかみさんがいろいろと見せてくれた。
子どもA:「あっ、いま、水みたいの でた!」
おかみさん:「生きているんだよ」
子どもA:「ちょっとさわりたい」
子どもB:「ぼくもー!」
子どもC:「これあいてる、なんでー?」
おかみさん:「そうね、これもあいているよ」
すると しばらくして・・・・
子どもD:「ねえー、はやくサバを買って もどろうよ」
子どもたち:「えっ、サバ??」
子どもD:「そうだよ、サバだよ」
子どもA:「ちがうよ、イワシだよ」
しばらく「サバ」か「イワシ」かの相談。
話し合いの結果、「イワシ」を5匹買って帰ることに。
帰り際、「何か聞いておきたいことある?」と保育者。
子どもE:「どうやって、ぜんぶの魚を止めてるんですか?」
おかみさん:「そうだねー」と、魚の〆方を教えてくれた。
おかみさん:「難しかったかな? 分かった?」
子どもE:「うん!」
********************************************************
確かにちょっと難しい話しだなァって、思いながら聞いていた。
でも、「魚の〆方」が分かったかどうかが 大事ではないのだろう。
子どもが、自分の経験や 知っている言葉を総動員し、
「魚と対話」するからこそ、「ぜんぶ動いていない」
「どうして止まってるのかな」 「なんかおかしいな」って気がつき、
〆ることで「止まる」ってことが分かったんだと思う。
こうして実感を得ながら 納得していくことが、
より意味のある「学び」になっていくんだろうな。