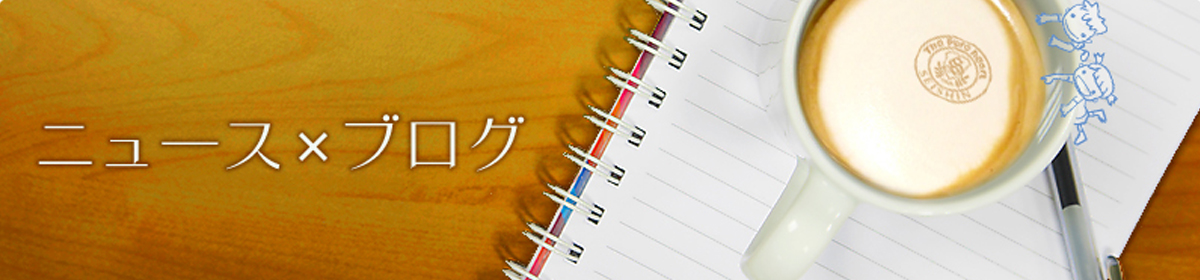群馬大学生の授業が幼稚園の子どもたちを通して
行われています。
2週続いて幼稚園でワークショップがあったので、
昨日は、大学の講義室での振り返りになりました。
(オブザーバーとして参加しました)
学生さんたちの振り返りや計画の中には、
企画者から、偶然できた色について「何色ができた?」と
子どもに問うているフェーズがだいたいあって、
子どもたちは、「オレンジジュース色」「ぶどうジュース色」
「コーヒー色」・・・・などど答えていました。
ここで、あ、なんかへんだなって思ったのです。
そう、いろいろな色ができているのに、
そのほとんどが飲み物の色になっているのです。
液体が飲料に直結するのか?とも思ったのですが、
それより入れ物(ペットボトル)が要因な気がします。
もし、たとえばジャムの瓶で作っていたら違ったでしょうか?
これは今後検証してみる価値がありそうです。
ぜひ、ご家庭でも色水をいろいろな容器に入れたり、
載せたりして試してみてください。
そして、結果をぜひ教えてください。
おもしろい研究が生まれるかもしれません。
カテゴリー: スタッフ通信
夏期保育の下見へ
今年も年長児は、7月下旬に夏期保育(4日間)に行きます。
空梅雨らしく湿原がカラカラで、これまでにない状況でした。
山をハイキングしたり、友だちと遊んだり、泊まったり、
ワークショップをしたり、楽しめること盛りだくさんです。
宿泊先から見た朝の景色。
この時間、この場所だから見られる素敵な景色。
そんな景色を見ながらいただく朝食。
コーヒーがより美味しく感じます!
(ある日のスタッフルームの風景)
清心では子育てしながら保育している
保育者の割合が多いです。
いろいろ両立させるのは大変だと思いますが、
私たちは、生きがいや、やりがいがもてる
環境の保障に努めていきたいと思っています。
こども園は保育時間も長いので、社会にとって
とても必要なところとの認識をもっていますが、
保育者も同じように子育てしていくためには、
何がどうなっていったらよいのでしょう。
「保育の質」を高めるために、保育者の生活の質も
同時に考えていきたいものです。
【出張ワークショップ(清心幼稚園✕中島佑太)】@前橋駅前ままマルシェ
今年もご依頼をいただきまして(アリガトウゴザイマス!)
前橋駅のロータリー横でワークショップを開催しました。
このイベントのテーマはファームなので、
今回の企画はマイバック(&ファーム化)づくり。
計画と中身は一致しないこともありますが、
それぞれに楽しんでいたようです。
======================
写真は、会場にいた在園の子どもにカメラを
預けている間に撮影されていたものです。
撮影者が子どもになると、目線の高さも角度も
私たちとは違っているだけでなく、撮りたいものを
撮っていていいなって思いました。
(ワークショップから帰る親子も納まっていました)
今週末は「ままマルシェ@前橋駅前」へどうぞ。
土曜日にままマルシェがあります。
よかったら遊びにきてください。
ワークショップ(マイバックをつくる(予定))を
出店準備中です(ナント無料)。
「前橋ままマルシェ」facebook。
(下見)あかぎやまへ
本日、遠足の下見で赤城山へ行ってきました。
園外で保育するときの下見は欠かせません。
普段よく町の中に子どもたちが行くことがありますが、
そのときも毎回下見をしています。
町の中の下見であれば、交通事故の危険予測や、
行き先となりそうな商店のオーナーとの打ち合わせ、
どの道を歩くだろう?…といった想定があります。
一方、山登りとなると、だいぶ勝手が変わりますね。

実際に歩く登山道と、クラスの子どもたちの歩く姿を重ねて
期待される道かどうかを想像したり、保育者が何人くらい
必要かを考えてみたり、トイレの状況をチェックしたりします。
その結果、毎年微調整しながら、計画を立てます。
それと、もう一つ。大きな違いがありまして、
それは自分自身と山との対話(もはや一人格闘技です)
同じ山なのに、なぜか、毎年大変になっていく・・・
自分の身体が維持されていないことを痛感し、
それは、下見を通して今年も本番が行けそうかどうか…
そんな判断をする日でもあるのです。
【見学&お祝い】ちぐさこども園(沼田市)へ行ってきました。
【第69回保育学会2016】「保育の質」を高める実践研究はどこへ
「保育の量」が足りないという一方、
「保育の質の最低限の部分」と、
「本当の意味での保育の質の向上」は、
どちらも切り離さずに考えたいもの。
保育が足りないと言って、急な拡大のしわ寄せで
命がなくなる現場では困ります。
しかし、そうした現状が国内で起きています。
それでは、もちろんいけないのですが、
「保育の質」に関する研究は、実践も絡んで
より多面的になってきたと感じます。
ただそれらは、〇〇式のように分かりやすい
早期的な教育ではないので、
評価や手ごたえが見えにくいです。
(ちなみに本園は、たとえば、カードを瞬時にめくって
記憶させる〇〇式や、高い跳び箱を飛ぶ等の〇〇式に
現時点で共感していません。そういう塾等も同様です)
だからこそ、エビデンスをもとにした地に足のついた
実践研究が必要ですし重ねていきたいと思っています。
園とご家庭で保育(教育)の方針が異なりますと、
対話が起こりにくくなりますので、これから
何かを選択されるようでありましたら、よくよく
お考えくださっていただけたらと思います。
(もし、早期教育や〇〇式等に関心がおありで、
そういったご家庭の教育方針があるようでしたら、
そうしたメソッドを導入している園もあります)
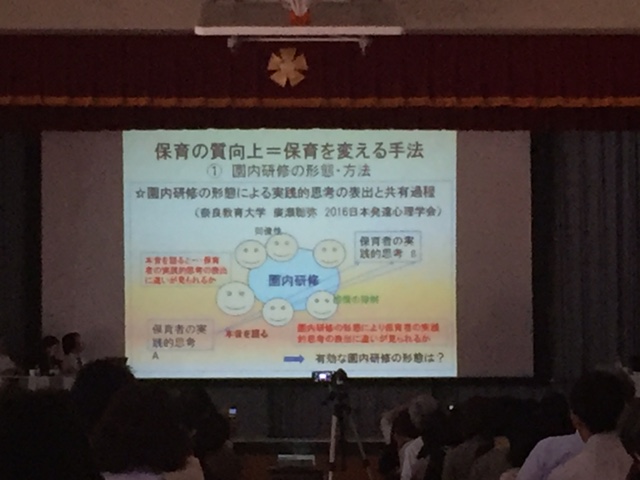
(今回の保育学会より@東京学芸大学)
あるクラスの壁面。
こんな遊び感覚で飾られていました。
みなさんは何に見えますか?
園では保育者が壁面をつくるというよりも、
子どもたちの何かを飾ったり、
園生活の過程で何かを見せたりといった
空間(平面)の一つと思っています。
ところで、よくカラフルでカワイイ系の2頭身うさぎや、
くまが遊んでいる姿などを飾っている所もありますが、
アレってどうしてこんなに広まったんでしょう?
(「保育室・壁面」で画像検索すると・・・・)
子どもの個性を大事にしています、と聞く一方で、
保育室が画一化されている不思議。
そうならないように心掛けたいものです。
【第27回発達心理学会】@北海道大学
明日は5月というのに札幌は吹雪もよう。

寒暖差20度以上。

会場内は熱い。
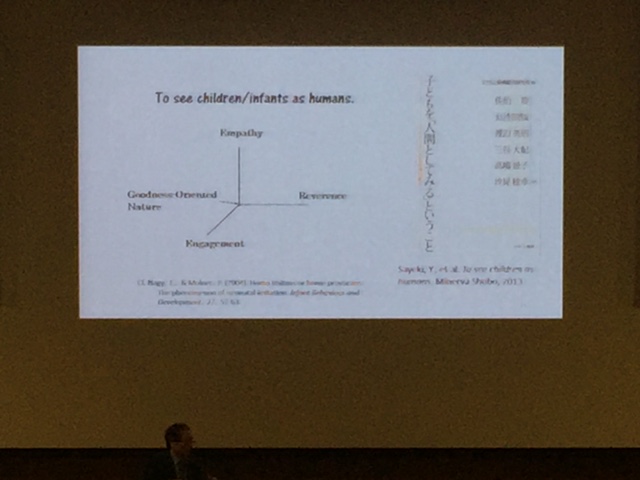
なかでも、佐伯胖氏とレディさんとのやりとり。
佐伯先生も熱かった。
【学会招待講演】
「なぜ社会的認知において「関わり合い」が重要か?」
●講演者Vasudevi Reddy
●指定討論者:佐伯胖
================================
ヴァスデヴィ・レディ 著 佐伯 胖 訳
『驚くべき乳幼児の心の世界
「二人称的アプローチ」から見えてくること』(ミネルヴァ書房)
(以下引用)
乳幼児はどのように人の心を理解するのか?
――この謎を解く鍵として本書が提起しているのが
「二人称的アプローチ(second-person approach)」である。
そこから、乳幼児が生後数か月で、すでに他者の
多様な心がわかっており、それらにきわめて
「人間的な」応答をしているという、従来の心理学研究では
描かれてこなかった驚くべき心の世界が浮かびあがってくる。
(原書:Reddy, V. 2008 How Infants Know Minds. Harvard University Press. )
[ここがポイント]
◎ 「二人称的アプローチ」という、人の心の世界に迫る新たなアプローチを提言。
◎ 従来の乳幼児の他者理解についての研究が見落としてきた、赤ちゃんの深い人間理解に根ざした、「ひとの心」の理解とかかわりを、あますところなく次々と明らかにする。