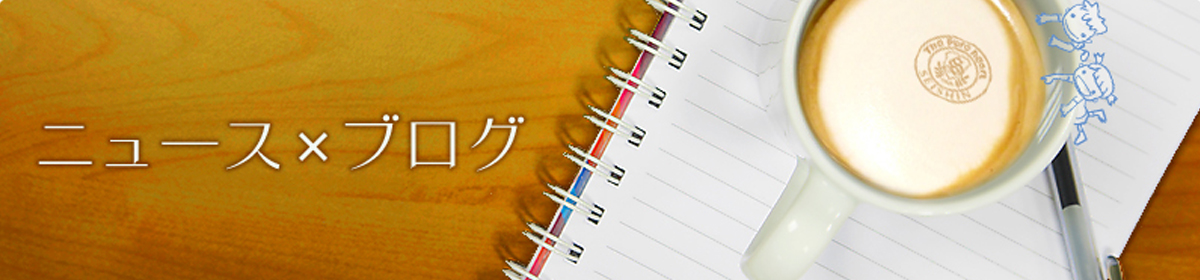「対話を通して変わる保育実践の創造(1)
園外研修の作り方と保育の質」をテーマにして、
幼児教育実践学会でポスター発表をしてきました。
少し広いスペースでしたので、私たちがこれまで
研究会で使用した保育写真も豊富に掲示しました。
実は、今回のように他園(※1)の保育者たちと一緒に
研究したり、発表したりするのは珍しいですが、
2年近く保育実践を交換(※2)しあっています。
さらに、こうしたテーマの研究も少ないです。
(それは今回発表して感じたことでもあります)
そのせいもあってか、始まって間もなく多くの方が
足を止めてくださいました!
全国から参加してきた保育関係者たちと
プレゼン的、対話的に進んでいきます。
たくさんのコメント、感想もいただきました。
これを今後に生かしていきたいですね。
(各園のみなさまお疲れさまでした!)
(※1)他園について
・ちぐさ幼稚園(沼田市)
・いそべこども園(安中市)
(※2)保育実践を交換
・およそ2か月に1回、保育者が自主的に集って、
保育実践を対話的に交換する場をもっています。
(「保育実践研究会@ぐんま」を運営しています)
・私立の保育施設では、各園の保育が異なり、
地域やその園の文化にも左右されます。そこで、
そうしたことをふまえつつ、子どもにとって本当に
「質の高い保育」とは何か?考え合っています。
カテゴリー: スタッフ通信
【お知らせ】夏期休業になります。
8月10日~11日:希望保育(8:00~)
8月12日~15日:夏期休業
週明けの17日からはいつも通りです。
どうぞよろしくお願いします。
【研修】子どもと保育実践研究会に参加しています。
昨日と今日は、園が積極的に参加したいと考えて
参加している研究会(「保育新時代の創造 Part1」)。
保育の研修や研究会は、県や市、私立幼稚園協会、
認定子ども園協会をはじめ、保育者養成系の大学、
NPO法人、企業・・・多様な主催・場所で行われている。
でも、内容は様々。
おもしろそうなモノ、難しそうなモノ、
よく分からないモノなどいろいろだ。
だから、これだけは!と思える研修会を選んで、
できるだけ多くのスタッフで参加している。
このところ、その対象になっているのが、
「子どもと保育総合研究所」の研究会。
(森上史朗先生の話も聞くことができた!)
そして、受講するだけに終わらないのが、
この研修会の特徴。
一緒のクルマに乗って行き来しているので、
帰りの車内で、早速、意見交換する。
たぶん、それが、この園のいいところ。
経験年数も性格も違う保育者の集まりだけど、
チームとして機能するのに必要なチカラは、
こうして紡がれていくのだと思う。
ワークショップ(@岡本太郎美術館)へ
本日、なかじ(中島佑太)のワークショップが、
川崎市岡本太郎美術館でありました。
9月1日からの展示を控えたこのプレベントに、
私たちも影のお手伝いとして参加してきました。
参加者は、子どもから大人までナント60名!
夏休みに入ったからでしょうか?
(やっぱり作家の人気でしょう!)
作ったものを参加者で鑑賞しました。
これらの一部は作品として展示される予定です。
【研究】保育実践研究会@ぐんま
昨年までは、7月も後半からは、夏休みに入って、
子どもも保育者も休みでした(一時保育を除き)。
今年からは、子ども園になったので、いつもの
半分くらいの子どもたちが通っています。
一方、私たちは、夏の時期に研修会や、学会の発表など
保育の勉強が続くので、保育者も保育状況に合わせた
変則的なシフトを組んで対応しています。
昨日は、県内の他園の保育者たちと、8月の学会で
協同発表をするために、自主的な研修会。
「保育の質」を本気で考えようとする他園の保育者たちと
意見交換するのは、刺激的な学びがあります。
そういう園や、保育者が増えていくことが、
子どもにとって、地域にとって、きっと大事です。
【ご案内】中島佑太ワークショップ(「遊びひらく岡本太郎展」)
企画展「遊び ひらく 岡本太郎展」に、現代作家の
中島佑太(なかじ)が出展します。
展示期間:9月1日(火)~10月4日(日)
来館者が作品を作ることができる、参加型の展示です。
会場内で、会期中毎日作品作りに参加できます。
(以下、企画展「遊び ひらく 岡本太郎展」HPより)
■プレワークショップ「おはなしの国の花畑」
身近な素材を使って、おはなしの国に咲く花をつくります。
できあがった花は、作品の一部として会場に展示されます。
日時:8月2日(日) 13:00~15:00
対象・定員:5歳以上だれでも・30名
参加方法:要申込。詳しくは「お申込み方法」をご覧ください。
応募しめきり:7月26日(日)
■作品に参加しよう!
見に来た人がつくったり、体験したりして楽しむこともできます。
★の日程で、中島さんも展示会場にやってきます!
日時:9月1日(火)から10月4日(日)まで毎日開催 9:30~17:00
★作家滞在日程:9月5日(土)、6日(日)、19日(土)、20日(日)ほか、
詳しくはHP等で告知します。
参加方法:申し込み不要!いつでも、どなたでも参加できます。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
こんなふうに太郎さんの作品に座ることもできます。
先日のレセプションでの中島佑太(なかじ)。
「まだ、ぼくの作品ないけど、ハハハ」と言ってるところ。
ぜひ、行ってみて、参加してみてjください!
美術館は川崎市です(群馬からもそんなに遠くない!?)
【ワークショップクラブ通信】あっちがわとこっちがわをつくる。(2015/6/13実施)
毎月1回不定期で開催している『今月のワークショップクラブ』は、
略すと『こんわく』になります。
漢字にすると「困惑」、どうしたらいいかわからなくて
とまどう様子のことです。
ワークショップとは、
そんなどうしたらいいかわからなくて、とまどうようなことが
目の前で起こった時に、一歩目を踏み出してみたり、
立ち位置を少し変えて状況を見つめ直す視点を得たりすることが
できる場だと考えています。
さて、今月の『こんわく』は、
いつもとは少し違って、中島が講師を務める「〜〜」の講座の
一環として一般公開され、多数の見学者が来園する中、
《あっちがわとこっちがわをつくる》というワークショップを行いました。
あっちがわとこっちがわをつくるは、ケンカや対立を生み出す
ワークショップではなく、壁を通じて”向こう側”を自分たちでつくり出し、
向こう側にいる他者と対話するワークショップです。
(このワークショップは、2年前に清心幼稚園の
年中さんたちと遊びながら考えたワークショップで、
2013年に千葉県で初めて実施されたものです。)
まず、最初に⚪︎×クイズのような形式で、
参加者を2つのグループに分けていきます。
だいたい同じ人数に分かれる質問を探していくのですが、
これがいつもなかなかうまくいきません。
「どちらかと言えば赤が好きか?青が好きか?」
「パープルが好きか?ブラウンが好きか?」
「犬が好きか?猫が好きか?」
「清心幼稚園の卒園生か?他の幼稚園・保育園の卒園生か?」

などと質問していきますが、意外と半々にはならず、
「旅行に行くなら、イタリアか、北海道のどちらに行きたいか?」という
絶妙な2カ所を比較した質問でようやくチーム分けが成立しました。
次に、イタリア派と北海道派が、それぞれ真ん中に引かれた線を
越えられないようにするために、用意した大量の新聞紙と
養生テープを使って真ん中に1つの壁をつくっていきます。
大人を対象に壁作りを行うと、効率良く壁を立ち上げる方法を
考える傾向があり、シンプルな壁になることが多いのですが、
子どもたちは効率的な作業なんてお構いなしなので、
「これは壁になるのか!?」と、不安にさえなるものができていき、
想像もできなかった形の壁ができたり、壁との関わりが生まれたりします。
今回は会場となった清心幼稚園のホールの床を全て新聞紙を
広げて埋め尽くしていたことも影響し、まずは敷かれている新聞紙が
真ん中に集められて山ができました。
あくまでお題が「壁」だったので、この山の上にひょろっとした壁が
立ち上がったのですが、この2段構造の壁がとてもおもしろい関わりを
生み出していきます。
この壁はもともと、イタリア派と北海道派が行き来できないように
するために建てらてた国境線のようなものなのですが、
一度広げた新聞紙を集めて山にしているため、
下の段はふわふわな新聞紙の山なので、掘って突き進むと
壁の向こう側に抜けられることを発見した子たちによって、
まるで、密入国するための抜け道がいくつもできていきました。

特に厳しい処罰はありませんが、このワークショップの唯一のルールは、
お互いの間に引かれた線を越えてはいけないことくらいです。
ただの線だけだとうっかり越えてしまうかもしれないので、
壁をつくります。
お互いを分断するための1つの壁を、
両側のチームの共同作業でつくっていくところに、
このワークショップの妙なポイントがあります。
だんだんと壁の背が高くなってくると、お互いが見えなくなってきます。
見えなくなってくると、お別れしてしまうようですが、
向こう側にいる人たちと何かコミュニケーションを
取りたくなるのがもう一つのポイントです。

新聞を丸めて投げてみたり、穴を開けて向こう側を除いてみたり、
秘密の抜け道をつくったりと、お互いを分断したことが
逆に壁を通じた新しいコミュニケーションを生み出し、
考え方(選んだこと)の違いで壁の反対側に立たされた人たちの中にも、
普段仲のいい友達がいたりと、人と人の関係性が浮かび上がってきます。
私たちはそれぞれ違う人間同士です。
考え方や好きなものなどはみんな違います。
その違いを受け入れることがなかなか難しい時があり、
しばしば私たちはケンカをしたり、すれ違ったりしてしまいます。
友達同士のケンカならまだしも、集落同士の争いや差別、
国同士の戦争にもなったりします。
アートは、学問の中では唯一他の人と答えが違ってもいい、
正解のない分野だと言われています。
足し算の答えがみんな違ったらちょっと困っちゃうかもしれませんが、
アートはみんな違っていいんです。
そんな考え方が社会のベースになったらいいなー。
(記:中島佑太)
就職説明会がありました(就職活動中の学生のみなさまへ)。
最近、保育士不足と聞きますが、実態はどうでしょうか。
大都市圏はとくに顕著で、企業保育園の積極的な
採用活動を耳にします。
群馬県では、昨年から幼稚園教諭、保育士をめざす
学生を対象にした説明会が開かれるようになりました。
本日、その説明会が市内某所で行われ、
熱心な多くの学生さんとお会いしました。
清心幼稚園では、数年後を担う保育教諭との
出会いを探しています。
2016年度の新規採用を検討していますので、
関心のある方がありましたら、ぜひエントリーください。
お待ちしています。
なお、群馬県は下欄に記載しましたが、一定の取り決めがあり、
適性検査を受けることになっています。
(また、10月1日以前の採用や内定および試験はできません)
【採用試験エントリーについて(専任)】
■エントリー期間:10月1日から予定数に達するまで
■対象者:新卒および第2新卒
保育士資格と幼稚園教諭免許状取得者(見込み可)であること
■試験内容:面接ほか(個々に応じて異なります)
●給与:経験・能力を考慮の上、規定により判断
●休日:土・日・祝日(行事等があれば出勤)、年末年始、お盆 等
●社会保険、健康診断、出産・育児制度あり
*園の見学やボランティアについては別途ご相談ください
*エントリー及びすべての連絡先:027-231-2415
***********************************************
県内の私立幼稚園に就職希望者は、8月29日に実施される
「群馬県私立幼稚園・認定こども園 教諭・保育士適性検査」を
受検することになっています。
適性検査は、7月中に申し込みが必要となりますので、
詳しくは「一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会」へ
お問い合わせください。
〒371-0854前橋市大渡町1丁目10-7
県公社総合ビル6F私学センター内
TEL:027-280-6206、FAX:027-280-6208
幼稚園の上空がすごい。
【研修】興味のあるテーマの話を伺って。
(以下、主催者(一般財団法人生涯学習開発財団)
の方からご案内をいただきました)
多元化共生社会におけるコミュニケーションシリーズ第8回
「「アートによる教育」を考える~アート・学び・公共性~」
グローバル時代の教育が始まろうとしている現在、
アートと学びと公共性について私たちはもう一度問いなおす
必要に迫られています。
そのために今回はデューイ研究をアートの切り口から
取り組んでいる上野正道氏(大東文化大学准教授)に
講演をお願いしました。
特に、学校関係者を始め、教育関係、アート関係の皆さんには、
次期の学習指導要領についての話題がいろいろと出ている中、
「アートの教育」と「アートによる教育」の位置付けを確認して
いただければと幸いです。
講演 :上野正道氏 (大東文化大学文学部准教授)
ナビゲータ:苅宿俊文氏 (青山学院大学社会情報学部教授)
++++++++++++++++++++++++++
内容も、出演される先生もどちらも関心が高く、参加してきました。
苅宿先生は、昨年本園にもお見えくださり、園での
ワークショップの様子を見学されたり、保護者の方へ
講話してくださっています。
学びの世界、とりわけ社会と学校教育における混沌さに
向かっていく視点は、人間がヒトとしてどう生きていくか、
それはいつも実践とつながっていて、
私たちが保育現場で、子どもたちと何を具現化してくか・・・
そうしたことにいつも向き合わされ、モヤモヤが増えます。
今回のテーマは、アートという切り口。
それは、園で日頃繰り広げられるアーティスティックな
子どもの姿とも重なります。
上野先生のお考え、お二人のやりとりに
もっとついていきたかったですが・・・
よかったら、みなさまもぜひ、それぞれの著作を。