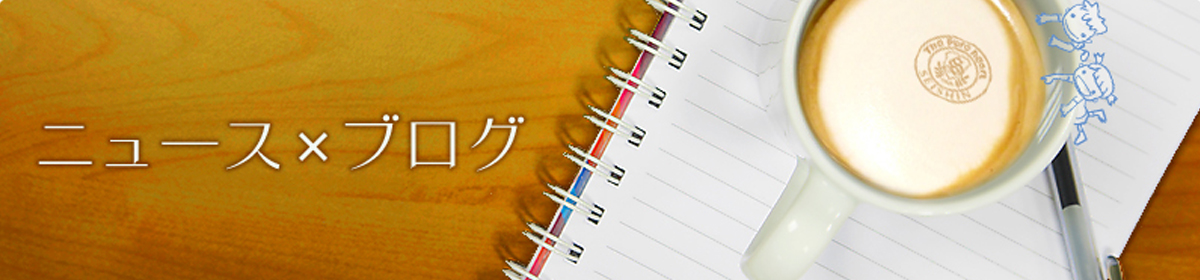1歳児の庭先にやってきていた。

なんという鳥だろう?
カテゴリー: こども(あそびの様子)
「なにいろ?」ときいてみる。
昨日、群馬大学の「造形表現」の実践授業があった。
今回の企画は、色水を使って色といろいろに遊びながら
親しむプラン。
先週から継続していて、用意しているものは、
・ペットボトル
・おはながみ(数種類の色)
・水
・絵の具
このくらい。
あいているペットボトルにおはながみをちぎっていれ、
水を入れてふたをする。それをいっぱい振ると、
おはながみの色が水に移って色水ができるのだ。
先週、子どもがいろいろに混ぜすぎだった、との振り返りから
今回はなるべく混ぜないで作る色を大事にしていくことになった。
ある3歳児は、自分が作ったものに興味をもっていたが、
色に対する反応よりも、その作ったモノ自体で遊んでいた。
それも、そうだろう。
企画者から、「これってなにいろ?」
っていう質問に対して「〇〇いろー」って答えるのは
まあ、普通に想像できる。
でも、〇〇色になった!とか、今度は〇〇色みたい!のように
答えながら展開する遊びはそんなに面白くないかもしれない。
(もちろん、企画者側の意図を読む必要もないだろう)
それに、何色かは、(ソレに)直接聞いてみた方が
きっといいに決まってる!
ながなわする!(雨に濡れても平気とか言って)
そうはいっても、泥も跳ねて、けっこう濡れる。
でも、また順番待ちを始めたりして。
いつもと違う感触でもあるのか、むしろ終わらない。
子どもも保育者もそのときのメンバーや
やり方で遊べることがいいなって思う。
あのシアターは続いていて、
階段の先がこんなになってきた。
(6/10のブログの続きです)
とどいたー!(2歳児)
子ども: ねー とどくー?
そんなことを階段の下の方から尋ねられました。
そこで、ぐーっと手を伸ばしてみました。
保育者:どーうー? とどいたー?
子ども:とどかなーい(笑顔)
さらに、めいいいっぱい手を伸ばしてみました。
保育者:どーうー?
子ども:とどかなーい(笑顔)
そんなことを繰り返すこと数回。
子どもが階段をテポテポとあがってきました。
そして、保育者の手元に来て――
子ども:とどいたーっ!
なんともいえない笑顔で手を差し出してきて、
おもわず手と手を合わせました。
それから、手をつないで階段をおりました。
下見の上映をしてみる
5歳児の部屋で、先日スタッフが夏期保育の下見で
撮影したビデオや写真を見てみることにしました。
本来なら5歳児15人のクラスですが、通りがかった
4歳児や3歳児が少しずつ入ってきてほぼ満員に。
4歳の子たち 「わたしもいきたーい」
そんな気持ちを持ってもらえると、
一緒に見た甲斐もあるものです。
どうやら階段が楽しいことに。
シアターができるのだとか(途中)。
どんなできあがりイメージなんでしょう??
まあ、待ってみましょう。
こんな使い方もある!(4歳児)
ときどき、確認にもどってくる!
ときどき、さらすなもいれてみる!
赤城山の親子遠足(4歳児・5歳児)
晴れれば目的の半分は目的を達したようなもの!
あとは大きなケガなく帰ってこられれば最高です。
そして、今日の遠足は、どちらもが果たされました!
(ホントほっとします)
現地では、それぞれの中にそれぞれの
体験があったと思います。

(こちらは4歳児たち)

そこそこにちゃんとした山登りですので、
タフな1日の方もいらしたかもしれません。
(4歳児;長七郎山 5歳児:地蔵岳)
ゆっくり休んでから、また日常の生活に
お戻りください。
みなさま、お疲れさまでした!
給食が届いたときにすれ違って。
子ども「あ!や、ら、む、た、さんだね」
子ども「うん、やぁー、らむた、さんだね」
そして「給食来たよー!」と、子どもが声をかけると、
近くにいた子が集まってきた(その認知とは別なのだ!)
(車からたむらやのおじさんが降りてくると)
たむらやさん:昨日のスープおいしかったろ?飲んだ??
子ども:(うなずく)
子ども:ねー、今日の給食なーにー?
たむらやさん:おじさん、知らないなー
子ども:カレー??
(給食をおろしながら)
たむらやさん:ん、今日はきらいなものいっぱいだな
子ども:え、なになにー?
たむらやさん:ネギとかナー
子どもたち:ネギ、だいすきー!!
たむらやさん:お、そっかそっか、ハッハハ
子どもとナイスな関係の“たむらや”さん。
食育はちょっとしたかかわりも味付けにナルのだ。