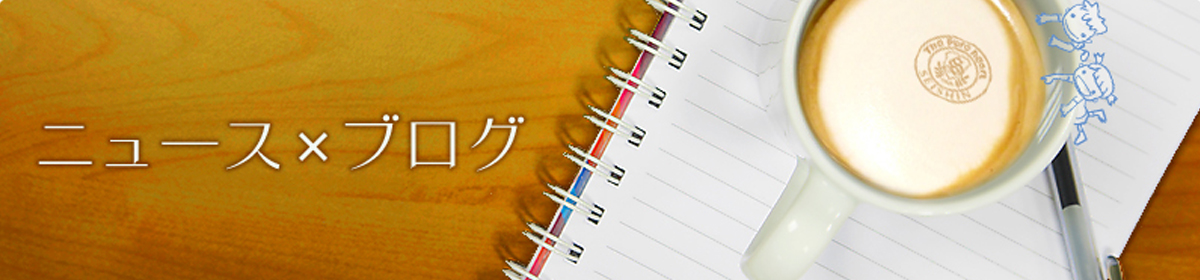「小学校が変わり始めた」と聞いて、
どのくらいが経過したでしょうか。
5年前、茅ヶ崎市の浜之郷小学校の実践を見たとき、
子どもと教師の関係性に驚きました。そして、
子どもたちが、実に楽しそうに学んでいるのです。
25年以上にもおよぶ この学校の取り組みは、
子ども、学校長、教師、保護者、地域、行政を中心に、
佐藤学氏を招いて 継続されてきたのでした。
これがモデルとなり、日本各地に広がっています。
その佐藤氏を招いたシンポジウム、
「対話的コミュニケーションとしての学び
『学びの共同体』の学校改革」が、
本日、東京大学福武ホールでありました。
氏は、「学校を一つつくること自体が難しい」と、
真に「協同する学び」を実践しようと改革する
学校の困難さを語っておりました。
ところが、それまで多くのアジア地域に見られた
一斉授業の形態が、韓国をはじめ、中国、台湾、
インドネシア・・・で、ここ数年、劇的に変わり始めた
というのです!(欧米はすでに変わっています)
日本でも同様かもしれません。すでに地域によっては、
「学び」の主体である子どもの声を聴き始めています。
それは同時に、子どもの「学びの地域格差」が
始まったとも考えられるでしょう。
そして、ここマエバシにも、学校改革に取り組んでいる
小学校(前橋市立山王小学校)があります!
(ご存知ですか!?内容はホームページをお読みください)
ここが「一つの小学校」となって、周辺に広がるといいと思います。
清心幼稚園でも、子どもが主体となって遊ぶ活動の中に
「学び」の姿をとらえようとしています。
主人公は子どもであり、それを支えるのが、
教師や保育者であるならば、小学校も幼稚園も
その役割はきっとかわらないでしょう。
そうすれば、幼稚園から小学校への接続も
さらにスムーズになっていくと確信しています。
コンテンツへスキップ